|
(→これは、巳年新春旅(5)のつづきです)
2025年、巳年のお正月は、関東を旅することにした。 今回の目的は、押し鉄の先輩方にお会いすることである。 「押し鉄のススメ掲示板」で交流させていただいているが、 まだ一度もお会いしたことがない先輩方だ。 1日目の1月3日は、巳年のお正月にちなんだ駅スタンプを集めながら、 常磐線の柏駅まで来て、投宿した。 今日4日は、この辺りが地元の押し鉄の先輩、江戸川台さんとお会いする約束をしている。 「江戸川台」は、お住まいの最寄り駅で、この柏駅から大宮まで通じている東武野田線の、 江戸川台駅からつけられた名前である。
|

| 今日も良いお天気で寒くない。良い旅日和になりそうだ。7:30少し前、柏駅にやって来た。 江戸川台さんとの待合せは、野田線の「流山おおたかの森」駅で10時、である。 それまで朝のうち時間があるので、久しぶりに野田線を少し散歩していく事にしよう。 |

|
柏駅
(東武野田線) デジタルスタンプ 東武アーバンパークライン愛称10周年 東武野田線は、大宮、春日部、野田、柏から船橋までと、東京の郊外の東側半分を ぐるっと回っている路線である。沿線には住宅地が多く、 東京へ通勤・通学する人が多く、利用客が多い。 東武鉄道としても幹線の扱いで、「アーバンパークライン」という愛称もつけられている。 この愛称が付けられて今年で10周年だそうで、今、記念のスタンプラリーが行われている。 |
| このスタンプラリーは「Wスタンプラリー」と銘打っていて、 デジタルスタンプとリアルスタンプの両方があるのだそうだ。 デジタルのスタンプが、柏駅にあるそうだ。 せっかくだから取得して行こう。ただ取得には、スマホに、東武鉄道専用アプリを ダウンロードしてユーザ登録する必要がある。昨夜ホテルでやったのだが、 結構面倒であった。そして改札の横の所に設置してあるQRコードを読み込ませたら、 このスタンプが表示され、取得できた。 |
|
柏駅
(東武野田線) 8000形 ただなんだか、画像を大きく表示することが出来ず、ちょっと不満の残るスタンプだった。 最近はこんな風に、鉄道会社毎に独自のデジタルスタンプが作られることもあり、 押し鉄としては、いったいどこまで集めるべきかと、考えてしまう。 でも改札脇の案内所に行くと、昔からある常設スタンプも健在であった。 ちょっと素朴感の残る、この8000形を描いたスタンプを押した。 やっぱりリアルスタンプの方が、安心感があるなあ。 |

|
| 「Wスタンプラリー」のリアルスタンプの一枚が、 電車に30分程乗れば行けそうな、七光台駅に設置されているようなので、 そこまで往復してみることにしよう。7:32発の大宮行に乗車する。 |

 2019年8月22日押印 |
豊四季駅
(東武野田線) 諏訪神社・成願寺 柏の街を外れると、沿線には畑が広り、のどかな風景だ。 豊四季駅に停車する。とても良い響きの駅名の駅だ。 5年ほど前の出張のとき、 仕事が終わった後、ここで降りたことがある。 目的は、この駅に残っている、貴重な戦前の駅スタンプを押すことだった。 その時押した印影を、左に再掲しておこう。 およそ90年前のものなので状態が悪く、 駅名以外は何が描かれているのかわからなかった。 それでも、貴重なスタンプが押せて、大変うれしかった。 |
| 電車は豊四季駅をあとにして、流山おおたかの森駅も過ぎ、路線名になっている主要駅、野田市駅へと進む。 周囲には工場が立ち並び「キッコーマン」のマークが入った大きな醤油タンクが見える。 野田では、江戸時代に醤油の醸造が行われ、一大産地として栄えた。ここで作られた醤油は、水運を使って、 大消費地の江戸に運ばれていた。 |

| 明治時代になると、水運だけでは醤油の運送が賄えなくなり、鉄道が熱望された。 それで出来たのが、千葉県の県営鉄道として始まった、この野田線であった。 野田から柏へ、そして常磐線に線路は繋がり、醤油は貨車で東京に運ばれた。 開通は1911年(明治44年)で、114年も前の事である。 |
|
七光台駅
(東武野田線) リアルスタンプ 東武アーバンパークライン愛称10周年 その後県営鉄道は民間へ払い下げられ、線路の延伸が続けられ、大正の終わりには、 総武鉄道が、大宮〜柏〜船橋まで、営業路線を繋いだ。 さらに東武鉄道に合併し、沿線の住宅開発が進んだ。 路線の役割は、やがて貨物輸送から人の輸送へと変化した。 8:08、七光台駅に到着。この駅の開業は、1968年(昭和43年)である。 周囲はまだ郊外ののどかさも感じるものの、住宅地が広がっている。 |

|

|
8:18発の柏行きに乗り、折り返すことにする。 まだ朝早い時間だし、お正月なのだが、結構沢山の人が乗車している。沿線人口の多さを感じる。 |

|
野田市駅
(東武野田線) リアルスタンプ 東武アーバンパークライン愛称10周年
8:26、野田市駅で下車する。「キッコーマン」の企業城下町にして、
「おしょうゆのふるさと」の街である。高架のホームに降りると、
周囲に広がる醤油工場の敷地の広さに驚く。 |
|
野田市駅
(東武野田線) おしょうゆのふるさと ようこそ野田市へ さらには、新しい駅舎を描いた新スタンプが、昨年設置されているので、 それも押して行く。このスタンプの印影は、こちらが地元の江戸川台さんに、 すでに頂いていた。駅舎の外に出てみる。なるほどこれは立派な駅である。 駅の正面には「萬」のマークがついた、巨大な銀色のタンクが見える。 きっとあの中には、大量の醤油が入っているのだろう。 キッコーマンの展示施設もあるようなのだが、今日はお正月だし朝も早いし、 開館していないので見学できないのが残念だ。前回来たときは、駅に着いた時間が遅すぎたし、 縁がない。またいつか、見学してみたい。 |
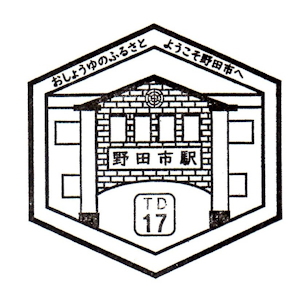 江戸川台さん先行押印 |

| こちらが地元の江戸川台さんから、この東武野田線の、総武鉄道時代の戦前駅スタンプの印影を、 いくつも頂いているので紹介しておこう。その中には、豊四季駅の1935年(昭和10年)押印の鮮明な印影も含まれており、 これで初めて、以前私が押したスタンプに何が描かれていたか知ることが出来た。 また当時は、野田町駅であったようである。市制が敷かれて野田市駅に改名したのは、1950年(昭和25年)だそうだ。 |
|
戦前・総武鉄道のスタンプ 江戸川台さんご提供 |
 |
 |
 |
 |
|
豊四季駅 |
野田町駅 |
清水公園駅 |
愛宕駅 |

| 合わせて、カラー印刷された「総武鉄道沿線案内図」の画像も頂いたので、紹介しておこう。 ここにはまだ、七光台駅も江戸川台駅も無いようである。 |

|
野田市駅
(東武野田線) 8000形 これからお会いする、江戸川台さんは、 ずっと昔に国鉄完乗を果たされている大先輩なのだが、 同時に、戦前の駅スタンプの収集家である。 今回もそうだが、いつも貴重な戦前駅スタンプの印影を ご提供下さっている。 私もコロナ禍の時に遠出が出来なかったことがきっかけで、 戦前スタンプに興味を持ち、 ネットオークションで落札して手に入れるようになった。 江戸川台さんは、こちらの方面でも大変な先達であるので、 ぜひお話をしたいとお願いしたのだ。 |
| 8:55、待ち合わせの、流山おおたかの森駅に向かうため、柏行きの電車に乗った。 しかしまだ時間があるようだ。9:07、江戸川台駅に停車したので、 ちょっと降りてみることにした。江戸川台さんのお住まいの最寄り駅である。 |

| 駅前に出ると、ちょっとした商店街があったが、お正月の朝の今は、 閉まっているお店が多くて静かだった。 その先には、一戸建て住宅が整然と並んでいる様子だ。 江戸川台駅の開業は1958年(昭和33年)。その時代に住宅開発で開けた町なのであろう。 江戸川台さんもこの町に家を持たれ、この駅から長年お勤めに出られていたのだろう。 |
|
流山おおたかの森駅
(東武野田線) デジタルスタンプ 東武アーバンパークライン愛称10周年 9:19発の電車に乗り、9:25、流山おおたかの森駅に到着。 駅名だけ読むと、駅前に大自然の森が広がっていそうな感じである。 が、全然そうではなくて、駅前は広くて新しく、高層のマンションが幾棟も立っている。 ここは、都心の秋葉原につながるTXつくばエクスプレスとの乗換駅でもあり、 とても大きなターミナル駅なのである。 ここには「Wスタンプラリー」のデジタルスタンプが設置されていたので、 QRコードをスキャンした。 |

|

|
さらにこの駅にも昨年、新しいリアルスタンプが設置されたので、押して行く。 この印影も、江戸川台さんから事前に頂いていた。 |
 江戸川台さん先行押印 |
流山おおたかの森駅
(東武野田線) 都心から一番近い森の街 まだ待ち合わせ時間まで30分ほどあった。 少し歩いて小腹も空いていたので、駅前のフードコートのミスタードーナツに入り、 コーヒーを飲み、ドーナツを食べて時間をつぶした。 さて、江戸川台さんにお会いするのが楽しみである。 どうして鉄道に興味を持たれ、どういうふうに国鉄全線完乗を果たされたのか。 戦前駅スタンプに興味を持たれたのはなぜか。そして、どうしてあんなに、 駅スタンプや鉄道に造詣が深くていらっしゃるのか、いろいろお聞きしてみたい。 |
|
待ち合わせ時間が近づいたので、待ち合わせ場所の、東武野田線の改札前に戻った。 すると、江戸川台さんから私のスマホに電話が入った。 江戸川台さんは、目の前にいらっしゃった。私より背の高い方である。 (→巳年新春旅(7)につづく) |
後旅 | 前旅 | 次章 | 前章 | 地区頁 | 扉頁
