|
今回の沖縄の旅、ゆいレール乗車と、世界遺産の城巡りが主な目的であった。 首里城、今帰仁城、座喜味城、中城城、勝連城と、順に巡り、4日目にして全部の訪問を果たすことが出来た。 2025年4月30日、13:10、勝連城からのバスで、コザのバス停に着いた。 次は、嘉手納に行きたいので、バスを乗り換えようと思う。 ここは「コザ十字路」という大きな交差点であり、バス停は行き先方面毎に別々だから、注意が必要だ。 信号を渡り、北側のバス停へ移動する。13:19発、琉球バス61系統・中部線がやって来た。これで良さそうだ。 |

| 乗ってすぐの、次の交差点名は「越来」(ごえく)だった。 私は迂闊にも知らなかったのだが、昔、ここに越来城というグスクがあった。 第一尚氏第6代の王、尚泰久が王子の時に守っていた城だ。 護佐丸・阿麻和利の乱のあとは、功績のあった大城賢雄に与えられた。 阿麻和利に嫁いでいた王女・百十踏揚は、大城賢雄と再婚し、ここで共に暮らした。 そういう歴史物語を良く知っていたのだが、ここを通過するまで、私はその場所を知らなかった。 |

|
沖縄戦の後、越来城はすぐに米軍に接収されたらしい。基地を作るために大規模な造成が行われ、地形が変わった。
立派だったグスクの石材も、建築資材として運び去られてしまい、今はほどんど残っていないらしい。
なので越来城は、あまり知られておらず、私も知らなかったのだ。
越来城の麓だったコザは、戦後、特に黒人が住む町として様変わりし、独特の文化で栄えたそうだ。
バスはやがて左折して、米軍の嘉手納基地の北側を走り始めた。 左の車窓は長大なフェンスが続き、その内側は芝生が広がり、住居や飛行場が見える。その広々とした様子に驚く。 嘉手納基地は東アジアでもっとも大きな米軍基地で、広さは約20平方キロメートル。嘉手納町の面積の80%はこの基地だそうだ。 |
 |
嘉手納駅
(沖縄県営鉄道) エキタグ/嘉手納歴史民俗資料室 甘藷発祥のまち 戦前日本軍は、この嘉手納に飛行場を作っていた。そのため沖縄戦では、米軍の集中攻撃を受けることになった。 比謝川の河口に開けていた古い嘉手納の街も一緒に壊滅し、何もかも失った。 以来そのまま、米軍の基地の街だ。13:44、嘉手納バス停着。 降りたところは、嘉手納ロータリーの一角だった。戦後ここに、アメリカ風のロータリーが作られ、 ここを中心に街が再建されて行ったのだ。 |
| ロータリーの道路の向こう側に、沖縄そばの店を見つけた。今日はまだお昼を食べそこなっているので、 大好きなソーキそばを頂いていこう。あっさりしたスープに、太めのちぢれ麺、そして豚のあばら肉・ソーキ。 沖縄グルメを語るとき、ソーキそばは外せない。この旅行ではまだ、しっかりしたものを食べてなかったので、満足した。 店には、たくさんの外国人の方がいた。きっと基地関係のアメリカ人だと思うが、彼らにもソーキそばは、 すっかり浸透しているのだろう。 |



| 店を辞して、ロータリーに沿って嘉手納町役場の方へ歩いていくと、立派な石碑を見つけた。 「嘉手納駅跡地」とある。ここの訪問が、嘉手納に来た目的である。 今は、ゆいレールを除けば、鉄道が無い沖縄だが、太平洋戦争前にはあったのだ。 ここは、那覇〜嘉手納間を走っていた、沖縄県営鉄道・嘉手納駅の駅跡だ。 |
|
嘉手納駅
(沖縄県営鉄道) 嘉手納歴史民俗資料室 最近、沖縄県営鉄道に関する「エキタグ」が、3か所に設置された。 ちょうど沖縄に行く事を考えていた私には、良いタイミングだった。 今回の旅で収集して行こうと思う。 嘉手納駅のエキタグは、この先の「かでな未来館」という建物の中の、 嘉手納歴史民俗資料室に設置されているという。 エレベータで2Fに上がっていくと、そこにこじんまりとした郷土資料館があった。 エキタグとリアルスタンプがあったので、さっそく押してみると、 戦前、嘉手納線を走っていた木製の車両と、嘉手納駅が描かれたデザインだった。 |
 |

|
昔の駅の周囲を再現した模型や、スタンプと同じ風景のジオラマもあった。 どこかのどかな、当時の嘉手納の様子が伝わってくる。 |
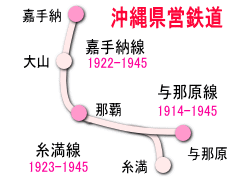
|
沖縄県営鉄道は、戦前、
那覇から3方向に、嘉手納線、糸満線、与那原線が運行されていた。軌間762mmの軽便鉄道で、
沖縄の人たちからは「ケービン」として親しまれていた。嘉手納線に関しては、大正11年(1922年)に開業した。
しかし残念ながら、沖縄戦で徹底的な破壊を受け、1945年に運行停止。以来現在まで復旧されていない、
戦後は、車中心の社会のアメリカ統治下だったからか、鉄道を復興しようという動きは無かったようである。 いまも「失われた鉄道」のままである。 |
| しかし、私は昨日も城巡りの後、読谷から那覇までバスに乗ったが、 夕刻の道路の混み様は酷く、バスは30分も遅れた。沖縄の道路の渋滞は慢性的らしい。 もしこの鉄道が復旧して現代まで存続していれば、沖縄の交通事情は、ずいぶん良かっただろうにと思う。 今後は沖縄にも鉄道は必要だろう。 整備新幹線を通したいという動きもあるようだ。 いつか実現することを祈りたい。 |
|
嘉手納駅
(沖縄県営鉄道) 比謝川河口の海岸 さて今回、沖縄県営鉄道の、当時の駅スタンプについて調べてみた。 すると、いくつかの印影が残っていることが分かったので、ここからはその印影も紹介して行こう。 印影は、押し鉄仲間の朱旅符さんからご提供して頂いたものである、感謝申し上げたい。 まずはこの嘉手納駅のスタンプであるが、比謝川の河口の名勝の様子が細かい線で描き込まれている。 それにしてもよくこの印影が残ったものである。おそらく戦前沖縄に旅行した人が、本土に持ち帰っていたものなのだろう。 沖縄に押印した紙が残っていたとしても、あの沖縄戦で焼き尽くされてしまっただろう。 沖縄戦では、実に人口の25%もの人が、命を落としたのだから。 |
 1935年押印 朱旅符さんご提供 |

| さて、2つの城を巡り、嘉手納駅のスタンプも押せたので満足だ、那覇に戻ることにしよう。 嘉手納役場前のバス停から、14:51発の琉球バス120号系統、那覇バスターミナル行きのバスに乗った。 走り出すとすぐに、左手の車窓は、また嘉手納基地のフェンスが続いた。 |
 1935年押印 朱旅符さんご提供 |
大山駅
(沖縄県営鉄道) 普天間宮洞窟 戦前の沖縄県営鉄道・嘉手納線の駅スタンプは、もう一駅存在していたようだ。 この大山駅のものである。描かれている普天間宮は、洞窟に琉球の古い神が祀られていたが、 尚泰久王の時に、日本の熊野神が合祀された。今でも多くの参拝客がある古社である。 当時、大山駅のあたりはサトウキビの栽培が盛んで、収穫したサトウキビを運ぶトロッコの線路が、 いくつも分かれていたそうだ。しかし、今はここも基地の街だ。 米軍普天間基地は、街のすぐ横で、騒音や事故の問題が多く、移転が望まれている。 ただ名護の辺古基地の拡張がセットになってしまい、国と沖縄県の間で合意が出来ず、進まない状況だ。 |
|
やはり道路は混雑し、那覇に近づくにつれ渋滞し、バスはなかなか進まなくなった。 やはりここには、快適な鉄道が通っていて欲しい。 手持無沙汰なので、ネットでいろいろ検索していたら、今日この後、ぜひ寄りたい所が出来た。 私は那覇バスターミナルより手前の、泊高橋というバス停で下車した。16:01。 ここは、離島への船が出ている那覇泊港のターミナル「とまりん」の前である。 ここから16:11発の、那覇バス7号系統のバスに乗り換えて、16:20、 県立博物館前で下車した。 |


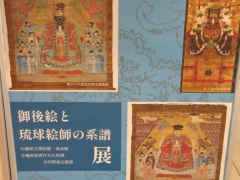
|
ここは2007年に開館した博物館・美術館の複合施設である。尚泰久王が鋳造した、
有名な「万国津梁の鐘」
が展示されており、それも見たいのだが、今日わざわざ寄ろうと思ったのには、別の理由がある。
沖縄戦では、日本軍の司令部が地下に置かれていた首里城は、米軍の徹底的な攻撃を受け、 何も残らない程、壊滅した。琉球王国の文化財もその時、ほとんど失われたと言ってよい。 しかしながら最近、焼失してしまったと思われていた貴重な絵が米国で見つかり、 沖縄に返還されたのだ。その絵は、 「御後絵」(おごえ)という。 |
|
沖縄県営博物館 博物館外観/重ね合わせスタンプ 琉球王国では、王が亡くなると肖像画を描いて残すのが習わしだった。 中国から冊封使が来て、王が国王として認証されたときの場面を描く、と決まっていた。 なので代々の王の「御後絵」が残されていたのだが、沖縄戦の後、行方不明になっていた。 それが4枚見つかり、返還され、 今日までこの博物館で展示されているというのだ。 これはもう、なんとしてでも見ておきたくなった。 |
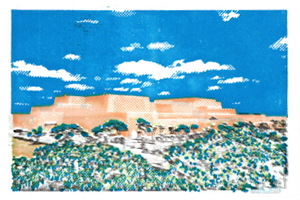 |
|
見事な極彩色の絵であった。4枚のうち3枚は、どの王様か特定された絵だったが、
1枚だけは傷みがひどく、どの王様の絵なのかはっきりしないそうである。
しかしそれでも良し、「王様、お帰りなさい」と声を掛けたくなった。
「万国津梁の鐘」の碑文にあるように、かつて海の貿易で栄えた琉球王国。
しかしその後、島津の侵略、琉球処分、沖縄戦と不幸が続き、今も悩ましい沖縄である。
そんな中、王様の絵が、アメリカから戻って来たのは、素晴らしい朗報だ。 |



| 博物館の外観を描いた、重ね合わせスタンプラリーがあったので、一応それに参加し、野外展示の琉球の古民家を見学した。 隣の合同庁舎前のバス停から、17:49発の那覇バス10号系統に乗る。那覇の街に戻って、どこかで夕食を食べていこう。 下車したのは、18:05、崇元寺前のバス停。降りるとすぐに、3つのアーチのある立派な石門がある。 ここには戦前まで、臨済宗の大きな寺があり、琉球国王歴代の霊廟であった。しかし沖縄戦で破壊され、今は石門しか残っていない。 私は過去の旅でもここを訪ねていたので、懐かしい。石門を潜ったところのガジュマルの木は、今日も迫力満点だった。 |
 2003年設置 購入印影 |
旭橋駅
(ゆいレール) 平成15年8月10日開業 少し歩けば牧志駅である。近くにとてもアメリカンな、 ハンバーガーのお店があったので入ることにした。 タコライスとジャスミンティーを頼んだ。タコライスの辛さをジャスミンティーが和らげてくれ、絶妙のマッチであった。
18:44、牧志駅からゆいレールに乗って、18:53、旭橋駅着、ホテルに戻る。
4日目の旅も終わった。明日はこの旅の最終日。本島南部を巡り、沖縄県営鉄道の与那原駅跡に行こうと思う。 |
後旅 | 前旅 | 次章 | 前章 | 地区頁 | 扉頁
